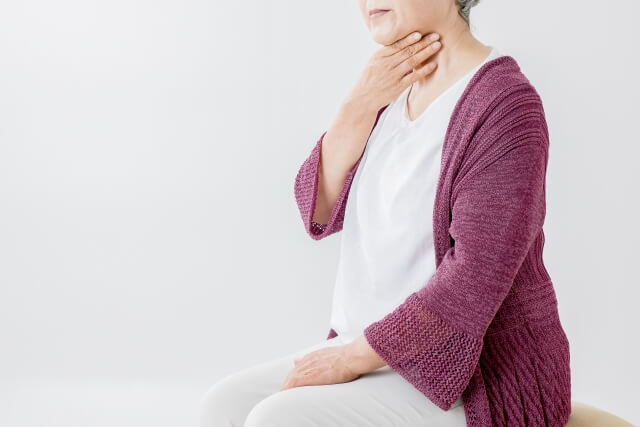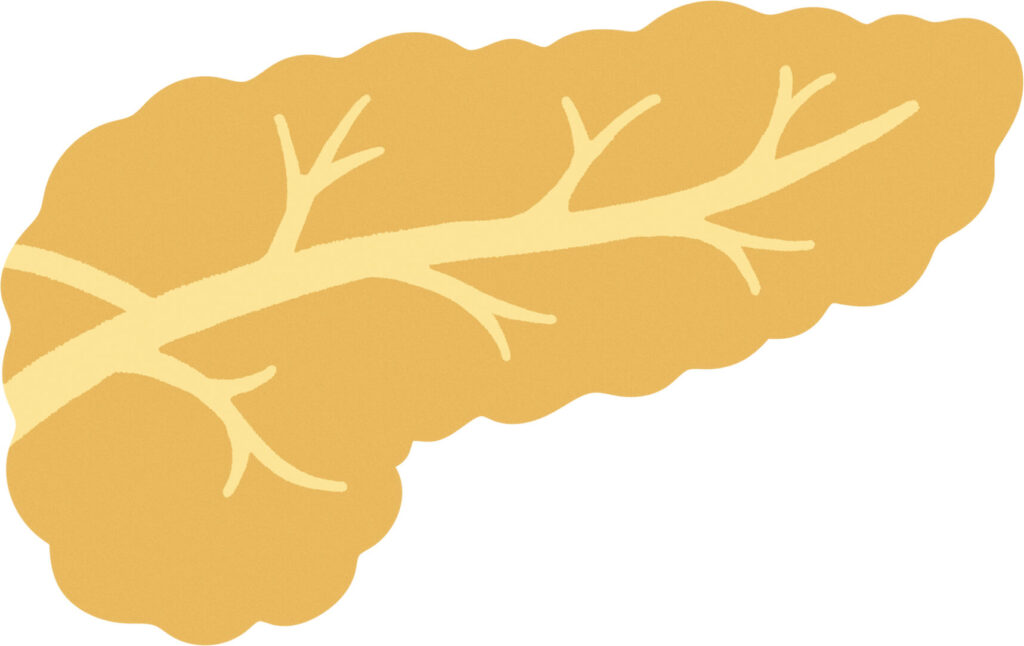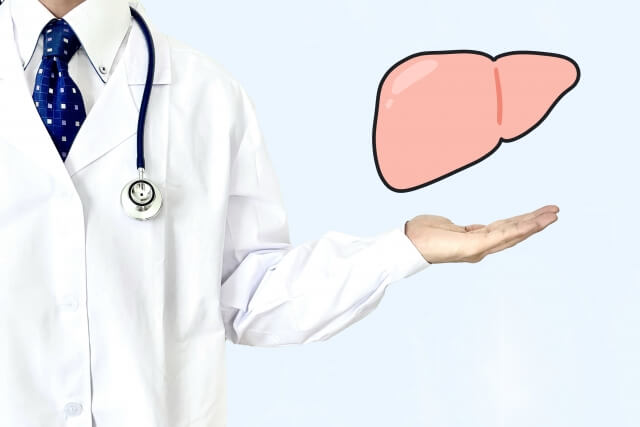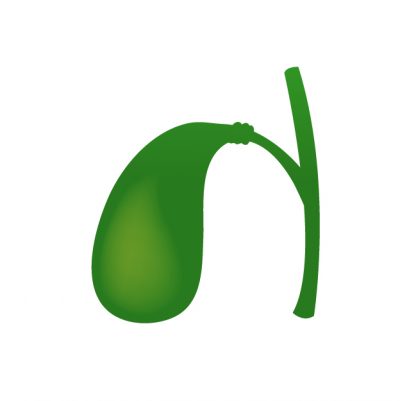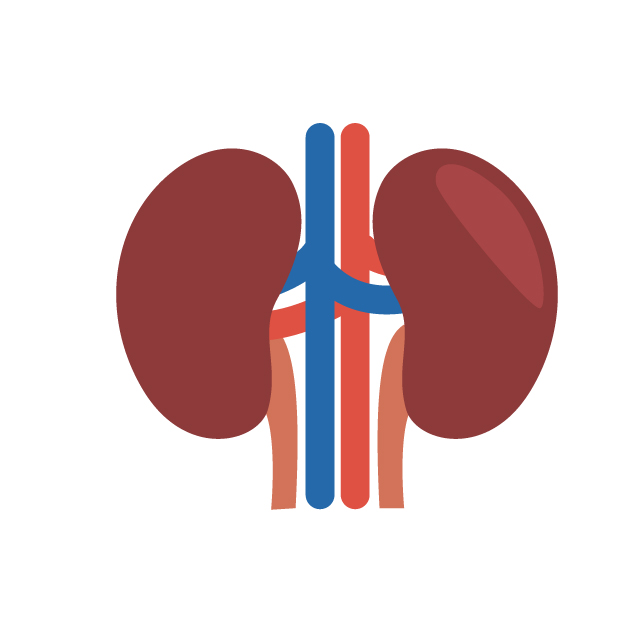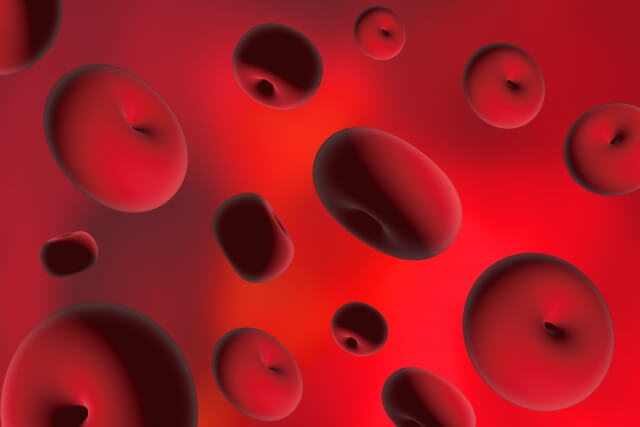癌(がん)– category –
-

肺がんの名医・専門医123名
肺がん全国の名医・専門医123名呼吸器内科、呼吸器外科 ※2024年4月更新 肺がんは19... -

大腸がんの名医・専門医142名
大腸がん全国の名医・専門医142名消化器内科、消化器外科、大腸外科 ※2024年4月更... -

胃がんの名医・専門医119名
胃がん全国の名医・専門医119名消化器内科、消化器外科、胃食道外科 ※2024年4月更... -

食道がんの名医・専門医63名
食道がん全国の名医・専門医63名消化器内科、食道外科 ※2024年4月更新 食道がんは... -

膵臓がんの名医・専門医82名
膵臓がん全国の名医・専門医82名消化器内科、消化器外科、肝胆膵内科、肝胆膵外科 ... -

肝臓がんの名医・専門医129名
肝臓がん全国の名医・専門医129名消化器内科、消化器外科、肝胆膵内科、肝胆膵外科... -

前立腺がんの名医・専門医77名
前立腺がん全国の名医・専門医77名泌尿器科 ※2024年4月更新 国内の前立腺がんの患... -

胆管がん・胆のうがん(胆道がん)の名医・専門医58名
胆道がん胆管がん・胆のうがん全国の名医・専門医58名消化器内科、消化器外科、肝... -

脳腫瘍の名医・専門医61名
脳腫瘍全国の名医・専門医61名脳神経外科 ※2024年4月更新 国内において年間約2万人... -

乳がんの名医・専門医182名
乳がん全国の名医・専門医182名乳腺科、乳腺外科 ※2024年4月更新 国内における乳が... -

子宮がん(子宮頸がん・子宮体がん)の名医・専門医134名
子宮がん(子宮頸がん・子宮体がん)全国の名医・専門医134名婦人科、産婦人科 ※20... -

卵巣がんの名医・専門医65名
卵巣がん全国の名医・専門医65名婦人科 ※2024年4月更新 卵巣腫瘍は、良性・悪性と... -

皮膚がんの名医・専門医42名
皮膚がん悪性黒色腫/メラノーマ等全国の名医・専門医42名皮膚科 ※2024年4月更新 皮... -

腎がんの名医・専門医49名
腎がん全国の名医・専門医49名泌尿器科、腎臓内科 ※2024年4月更新 腎がんには、腎... -

甲状腺がんの名医・専門医33名
甲状腺がん全国の名医・専門医33名甲状腺科、耳鼻咽喉科、内分泌・代謝内科 ※2024... -

膀胱がんの名医・専門医40名
膀胱がん全国の名医・専門医40名泌尿器科 ※2024年4月更新 尿路がん(腎盂、尿管、... -

血液内科疾患(白血病・悪性リンパ腫)の名医・専門医58名
血液内科疾患白血病・悪性リンパ腫等全国の名医・専門医58名血液内科・腫瘍内科 ※2... -

頭頸部がん(咽頭がん・喉頭がん)の名医・専門医50名
頭頸部がん咽頭がん/喉頭がん/舌がん等全国の名医・専門医50名耳鼻咽喉科、頭頸部...
1